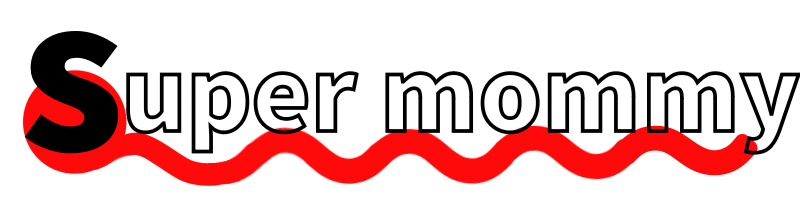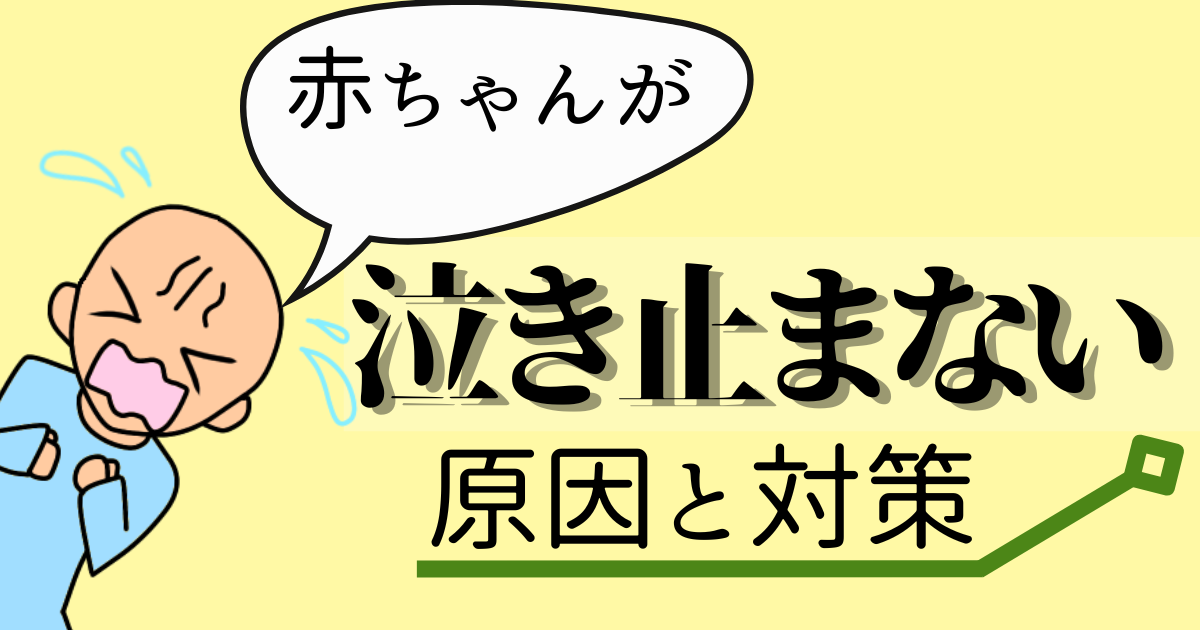朝、夕方、夜など特定の時に泣く時や、オムツやミルクも欲求は満たされているはずなのに大泣きする・・・
など赤ちゃんがなぜ泣いているのか困ったことありませんか??
特に0~1歳の間の赤ちゃんは原因不明で泣くこともあります。
赤ちゃんが泣いてしまう理由は分かりにくいですが、一般的な原因と対策があります。
ミルク・オムツ・睡眠 これらの欲求が満足している場合で、泣いてる時の原因と対策を説明します。
泣き止まない原因①:体調が悪いときのサイン
赤ちゃんが泣き止まないとき、その原因の一つとして体調が悪い可能性があります。
赤ちゃんの様子を見て、以下のサインを確認してみましょう。
1. 食欲がない
普段ならミルクや離乳食を喜んで飲んだり食べたりする赤ちゃんが、急に拒否する場合は、体調が悪い場合も。例えば、飲み物や食べ物を口に持っていっても顔を背けたり、口を開けなかったりすることがあります。
どうする?
- 赤ちゃんが普段よりも食欲がない場合は、無理に食べさせずに少し様子を見てください。水分補給さえ取れていれば、少しの間様子を見て大丈夫です。
2. 元気がない
いつもは元気に手足を動かしている赤ちゃんが、突然静かになってしまうことがあります。普段なら興味を持つおもちゃに反応しなかったり、目がどんよりしていたりすることが、元気がないサインです。
どうする?
- おもちゃで遊んでみたり、声をかけてみたりして、赤ちゃんの反応を確認してください。あまり反応がないときは元気がない証拠です。
3. ぐったりしている
赤ちゃんがぐったりしている場合、全体的に力が入らず、抱っこしたときにずっしりと重く感じることがあります。手足を動かさず、泣き声も弱々しいことが特徴です。
どうする?
- この状態は緊急性が高い可能性がありますので、すぐに医療機関に連絡し、診察を受けるようにしてください。
4. いつもと違う
赤ちゃんはまだ自分の不調を言葉で表現できません。そのため、普段とは違う行動や表情を見せることが、体調が悪いサインとなります。例えば、笑顔が少ない、抱っこしてもすぐに泣く、眠りが浅いなどが挙げられます。
どうする?
- いつもと違うと感じたら、まずは赤ちゃんの体温を測ったり、体を優しく触れてみたりして変化がないか確認してください。何か異常が見つかる場合は、医師に相談するのが安心です。
5. 顔色が悪い
顔色が普段よりも青白かったり、唇が紫がかっていたりする場合は、酸素不足や血行不良の可能性があります。また、顔が真っ赤になっている場合も、体温が上がりすぎているサインかもしれません。
どうする?
顔色の変化が見られる場合は、すぐに体温を測り、急いで医療機関に連絡しましょう。赤ちゃんの顔色が元に戻らない場合、早急に診察を受けることが重要です。
これらの場合、様子を見ても心配する時は遠慮なくお医者さんに相談してくださいね。
泣き止まない原因②:部屋の気温が不快なとき
赤ちゃんが泣き止まない原因の一つとして、部屋の気温が不快と感じている場合があります。
赤ちゃんは大人よりも体温調節が未熟で、気温の変化に敏感です。そのため、部屋が寒すぎたり、暑すぎたりすると、不快に感じて泣くことがよくあります。
寒すぎる場合の対策
冬場や冷房が効きすぎた部屋では、赤ちゃんが寒さを感じて大泣きすることがあります。赤ちゃんは自分で体を温めるのが難しいため、寒さに非常に敏感です。
どうする?
- 赤ちゃんが寒がっている場合は、部屋の温度を調整し、暖かい服やブランケットで包んであげましょう。ただし、過度に厚着をさせると逆に暑くなってしまうので注意が必要です。理想的な部屋の温度は18度から22度です。
- スリーパーはよく動く赤ちゃんにおすすめですよ、、
暑すぎる場合の対策
逆に、部屋が暑すぎる場合も赤ちゃんは不快に感じ、泣いてしまうことがあります。特に夏場や暖房が効きすぎた室内では、赤ちゃんは汗をかいて体温が上がりすぎることがあります。
どうする?
- 部屋の温度を涼しく保つために、適切なエアコンの使用や換気を行いましょう。赤ちゃんの服装も、通気性の良い軽い素材を選び、汗をかいている場合はすぐに拭いてあげることが大切です。
急な気温差に対する対策
赤ちゃんは急な気温の変化にも敏感です。例えば、外から帰ってきたときに室内が急に寒く感じたり、逆に暖かすぎたりすると、びっくりして泣くことがあります。
どうする?
- 外出先から戻った場合は、すぐに赤ちゃんの服を調整し、部屋の温度を確認して適切に調整しましょう。できるだけ急激な温度変化を避けるために、外から戻る前に室内の温度を整えておくと良いでしょう。
室内の気温設定
赤ちゃんが過ごしやすい理想的な室温は
18度〜22度の間
この範囲内であれば、赤ちゃんは快適に過ごしやすいです。
赤ちゃんそれぞれに個人差があるため、少しずつ温度を調整してみてください!
また気温に合わせて赤ちゃんの服装や部屋の温度を調整しましょう。特にエアコンを活用すると温度を調整しやすいですよ。
正しい気温がわからない時は、温度計を使って部屋の気温を確認しましょう。赤ちゃん用のおすすめの気温計もありますので、ぜひチェックしてみてください。
泣き止まない原因③:かまってほしい・甘えたいとき
生後2ヶ月を過ぎると、赤ちゃんは徐々にママやパパなど身近な人を認識し始めます。
この時期になると、ママやパパの姿が見えなくなると不安になって泣くことが増えてきます。赤ちゃんにとっては、「僕(わたし)を見て~!」という気持ちが強くなるのです。
赤ちゃんはまだ言葉で自分の気持ちを表現できないため、泣くことで「寂しい」「一緒にいてほしい」と伝えていることも。親としては、この泣き方が甘えたいサインであることを理解し、安心感を与えることが大切です。
スキンシップで安心感を与える
たくさんスキンシップをとる
- 赤ちゃんが不安になって泣く時には、抱っこやおんぶをして、できるだけ体に触れてあげましょう。スキンシップは赤ちゃんに安心感を与え、泣き止むことが多いです。
声かけを積極的に行う
- 赤ちゃんはママやパパの姿が見えなくても、声を聞くだけで安心します。「ここにいるよ」「大丈夫だよ」など、優しく声をかけてあげることで、赤ちゃんは安心しやすくなります。
家事中の工夫
- 家事などで手が離せない時でも、赤ちゃんに「ちょっと待っててね」などと声をかけましょう。数分でも赤ちゃんとスキンシップをとり、その後、ベビーベッドに置くと、意外とご機嫌で一人で過ごしてくれることもあります。
泣き止まない原因④:成長過程で泣く時
主に黄昏(たそがれ)泣き、夜泣きなどは成長の一貫として泣く場合があります。
これはどんなにあやしたり、抱っこしたり、満たされていたとしても、しばらく泣いていることが多い場合があります。
成長に伴う泣きへの対処法
ベビーマッサージを試す
- 泣き止まない場合、ベビーマッサージを行うことでリラックスさせ、泣き止むことがあるかもしれません。具体的な方法については別の記事で詳しくご紹介します。
漢方を取り入れる
- 生後3ヶ月以降の赤ちゃんには、漢方薬を試してみるのも一つの手です。ただし、必ず医師や薬剤師に相談のうえ、適切なものを選んでください。ドラッグストアでも購入できますが、専門家に相談してから選ぶとより安心ですよ。
お医者さんに相談
夜泣きが続いたり、かんしゃくがひどくなってしまった時は、遠慮せずにお医者さんに相談してみましょう!適切な対処法を提案してくれるので、安心して赤ちゃんと向き合うことができますよ。
赤ちゃんを泣き止ませる時にやってはいけないこと
激しく揺らす
赤ちゃんが泣き止まなくて焦ってしまうこともあるかもしれませんが、強く揺らすのはとても危ないので気をつけましょう。
赤ちゃんの脳はまだ発達途中で、激しく揺らすと深刻なダメージを受けることがあります
優しく抱っこして、そっと安心させてあげましょう。
口を塞ぐ
赤ちゃんが泣き続けると、お母さんも不安になってどうしたらいいか迷ってしまうことがあるかもしれません。
でも、泣いている赤ちゃんの口を塞ぐのは、実はとても危険なんです。
赤ちゃんはまだ口呼吸が上手にできないので、口を塞ぐと窒息してしまう可能性があります。特に泣いているときは息を強く吸い込むこともあるので、口を塞ぐことで酸素が不足し、命に関わることも。
赤ちゃんが泣き続けるとつらく感じることもあると思いますが、そんなときは、深呼吸をして少し気持ちを落ち着けてくださいね。泣き声に負けずに、優しく声をかけてあげるだけでも、赤ちゃんはお母さんの愛情を感じて安心するはずです。
まとめ
赤ちゃんがずっと泣き止まないと、お母さんも本当に疲れてしまいますよね。
そんなとき、何をしても泣き止まないと感じると、ますます不安になることもあります。でも、無理をしないでくださいね。
上記のことをやっても、赤ちゃんが泣き止まない…疲れた…と感じたら、親戚や知り合いなど、信頼できる人に頼ることも大切です。
頼ることは決して悪いことではなく、お母さん自身がリフレッシュして、赤ちゃんとまた笑顔で向き合うための大切な手段です。
しかし、どうしても周りに頼れない場合もあると思います。今は自治体などで赤ちゃんを預けられる制度があったりするので、ぜひ調べてみてください。
以上が赤ちゃんの泣き対策でした。

お母さんが笑顔でいられることが、赤ちゃんにとっても一番の安心です。
無理をせず、周りに頼りながら、少しずつ乗り越えていきましょうね。